「できなかったことができる」とはどういうことだろう?
できないということは、これまで意識したことがないということでもある。
それは、これまでスケートの4回転ジャンプをしたことがない人が、どういうものなのかイメージできないのと同じである。
できるようになるためには、あれこれ試しながら、「できない→できる」という変化を身体に起こさなければならない。
そんなの当たり前でしょ。と思うかもしれないが、本書ではこの問いに対して、科学的思考を効かせることで、考察を重ねている。
私たちは、自分の体を完全にはコントロールできないからこそ、新しいことができるようになるのです。
本書は、現在進行形の研究を手がかりに、5名の科学者及びエンジニアとの対話を通して、このできる科学を考えていく。
まさに目から鱗、ページをめくる度に新しい発見がある、そんな一冊だ。
目次
①桑田の投球術、ない尻尾を振る実験、サイレントスピーチまで
②「結果を同じするためにパフォーマンスを変える」という発想
③ウィスパーボイスはシフトキー
④「できる=優れている」「できない=劣っている」という価値観を覆す
①桑田の投球術、ない尻尾を振る実験、サイレントスピーチまで
本書の副題は、「できるを科学する<テクノロジー×身体>」である。
登場する科学者及びエンジニアは、決して誰もが知る面々というわけではないが、研究内容は飛び抜けて面白そうなものばかりだ。
元巨人・桑田真澄投手のピッチングフォームの解析から見えてきたのは、「精密機械」のイメージとは程遠い、毎回のフォームのゆらぎでした。「体に解かせる」からこそ環境に適応することができる、トップアスリートの世界をのぞき見ます。
脳卒中の患者さんが、麻痺した手を動かすための新たな神経経路を見つけるのを、どうやったら外から助けることができるか。「ないしっぽをふる」実験に、そのヒントがあります。
「音を出さずにしゃべる」など、インターフェイスとしての声の可能性に注目している暦本さん。
上記は一部であるが、今回、研究者たちをアテンドするのが、本書の著者で、他にも『目の見えない人は世界をどう見ているのか』『どもる体』等の著書で知られる、東工大「人類の未来研究所」センター長の伊藤亜紗さんだ。
人文社会系の研究者として独自の視点を持つ著者は、これまで数多くの名著を世に送り出してきたが、独自の視点は本書においても遺憾なく発揮されている。
本書では「テクノロジーと人間の体の関係」という古典的な問題を扱っているが、その視点はとてもミクロである。
つまり、多くの本で語られる「社会的な影響」や「人間的価値への挑戦」といった大局的な視点ではなくて、あくまで一つ一つの体の経験というミクロな視点から論じられている。
本書は、今までできなかったことをテクノロジーができるようにしてくれるかのように、読者に様々な「感覚」を擬似体験させてくれる一冊である。
②「結果を同じするためにパフォーマンスを変える」という発想
練習と本番は、仮説と検証の関係なんです
このように語るのは、ソニーコンピュータサイエンス研究所の古屋晋一さんだ。
古屋さんは、ピアニストの演奏技術を助ける方法を研究している。
では、トップレベルのピアニストとそうではないピアニストの違いはなんだろう?
古屋さんは音大で働いていたときに、いろいろな人に話を聞いてまわりました。「本番の面白さってどこにあるんですか」。すると「ふだん降りてこない演奏が降りてくることだ」という答えが返ってきた。ふだんと違うから怖くないんですか、と返すと、「それはいつも同じ演奏ばかりしているからだ」と言われたそうです。「トップの方は、ふだんからそうした探索をしてるのかなと思います」。
トップレベルのピアニストは、練習の時から「探索」を繰り返している。
大事なのはこの探索の質と幅だ。
探索の質と幅が十分であれば、本番でのパフォーマンスは良くなるだろう。
そして、元野球選手の桑田真澄の投球を研究するのは、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の柏野牧夫である。
精密機械と言われた桑田の投球を分析すると、投げる度にリリース位置がずれていたという、衝撃的な事実が明らかとなった。
ずれの幅は、最大14センチにもなり、ちょうど頭ひとつ分、前にずれつつ高さも低くなっていたという。
このずれは何を意味するだろうか?
要するに、桑田の投球は、「フォームは毎回かなり違うのに、結果はほぼ同じ」なのです。「変化するフォームから、安定した結果を出している」のです。
つまり、先述したピアニストも桑田も、「パフォーマンスが毎回同じ」ではなくて、「結果を同じするためにパフォーマンスを変える」ようにしていたということだ。
興味深いのは、両者とも、パフォーマンスを変えようと意識していたのではなくて、いつも通りと思っていたにも関わらず、パフォーマンスだけが結果的に変わっていたことである。
本書では、体の「ゆらぎ」「ノイズ」がこうしたパフォーマンスの変化を可能にしているという。
③ウィスパーボイスはシフトキー
そして、ビジネスマンであれば、東京大学大学院情報学環の暦本純一さんの章は絶対読むべきだ。
暦本さんは、これまで100以上の特許を取得し、『妄想する頭 思考する手 想像を超えるアイデアのつくり方』といった著書も出版しており、まさに業界屈指のアイデアマンである。
暦本さんの発明の一つに、スマートスキンがある。
スマホ等に表示されたテキストや画像が、小さくてよく見えないとき、2本の指で画面をつまんで自在に拡大表示することができる、あの技術だ。
実は、このスマートスキンは、スマホが世に出回る前に暦本さんらにより開発され、暦本さんが投稿した論文を読んだアップルが、スマホに取り入れたそうだ。
そんな暦本さんは、サイレントスピーチ、つまり声を出さずにしゃべる方法を研究している。
これは、病院のエコー検査で使われるような超音波プローブを喉にあてて、様々な口内の画像を撮影し、それをAIが学習するというものだ。
しかし、例えば「パ」と「バ」などは、唇を使う音であり、口内(口内と言ってもほとんどは舌の動きだ)の画像だけで音を判断することが難しいことがわかってきた。
そこで暦本さんが注目したのが、ウィスパーボイス(ささやき声)だ。
我々ってウィスパーと普通をしゃべり分ける能力を持った人間なわけですよ。それってシフトキーみたいなもので。だからモードに使えるんじゃないかと思っています。
この見立ては衝撃的だ。
わたしたちはパソコンのキーボードを入力するとき、左上のボタンは、通常、数字の「1」の入力に使われるが、同じボタンをシフトキーを押しながら使うと、「!」の意味になる。
暦本さんは、ウィスパーボイスがこのシフトキー(モードチェンジ)のように使えるんじゃないかと言っている。
この発想の転換の凄さ・・・。私の拙い書評では伝えきれないのが何とも悔しい。
ぜひ本書を確認していただきたい。
④「できる=優れている」「できない=劣っている」という価値観
私たちは、知らず知らずのうちに「できる=優れている」「できない=劣っている」という能力主義的な価値観にどっぷり浸かってきた。
これまで「できない」を多く経験してきた人間は、自分が劣っていると評価を下し、挑戦することを諦めてきたのではないだろうか。
しかし、子供の時は、誰しも「できない→できる」の楽しさをシンプルに味わっていたはずである。
本書は、そんな私たちの能力主義的な価値観から、今一度できることの楽しさを思い出させてくれる、そんな一冊だ。
この書評で紹介できたのは、本書の内容のほんの一部でしかない。
紹介できないのが心苦しいが、本書には、まだまだ興味深い内容がたくさんあるので、ぜひ続きは本書を読んで確かめていただきたい。





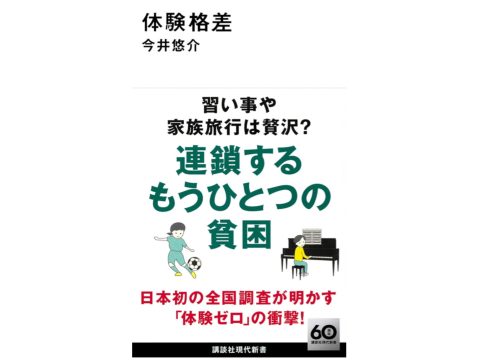
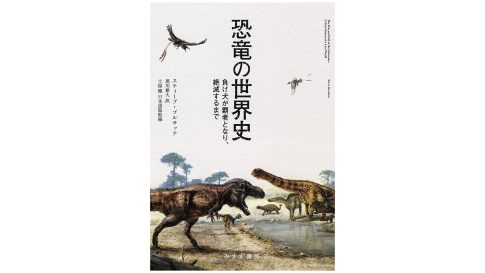



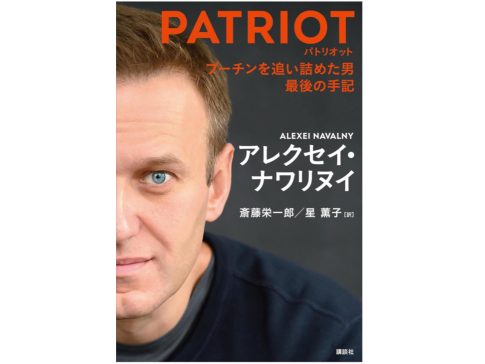




コメントを残す