時に言葉が私たちの思考を拡張することがある。
例えば、iPhoneという言葉が、その言葉一つで人々の電話という固定観念を一変させたように、本書の「性スペクトラム」という言葉も、性という言葉に対する人々の固定観念を一変させる可能性がある。
では、性スペクトラムとは何か?
スペクトラムと言えば、誰でも光スペクトラムくらいは聞いたことがあるだろう。
光スペクトラムとは、虹の橋のように、隣り合う2色の間の境界があいまいで連続している様のことを言う。
性スペクトラムは、この光スペクトラムと同様に、性(オスとメス)にも境界がないという考えだ。
本書は、この性スペクトラムという考えを提唱し、30年にわたり生物の性の研究をおこなっている著者による、まさに固定観念を覆される一冊である。
本書はLGBTQ+という考えに科学的な根拠を与える
そもそも、男は男、女は女という考えは、今や一昔前の考え方になりつつある。
近年は、従来のLGBTにQ(クエスチョニング:自らの性のあり方について特定の枠に属さない人)を加え、LGBTQと表現されることが多い。
さらに、このLGBTQにも当てはまらない人がいるという意味で、LGBTQ+と表現することすらある。
本書は、このLGBTQ+という考えに、科学的な根拠を与えるかの如く、性決定遺伝子や性ホルモンの働き、そして、細胞レベルでの性差について書かれている。
新書なので200ページ程度のボリュームであるが、それでも十分に科学的な好奇心を味わせてくれる一冊だ。
性の決定プロセスは多様である
しかし、性に境界がないと言われてもピンとこない人が大半だろう。
それもそのはずで、多くの人は、中学や高校で学習した性の知識で止まっているからだ。
そう、精子と卵子が出会ってXY染色体の組み合わせがどうのこうのという、あの話である。
確かに染色体のXYの組み合わせがオスになり、XXの組み合わせがメスになるというのは正しいが、本書によれば、これは性決定プロセスの第一ステップでしかないという。
実は、性腺原基は、染色体の組み合わせXYであろうがXXであろうが、精巣と卵巣のどちらにも分化することができる、という興味深い能力を備えています。
つまり他にも性を決定する要因がいくつか存在するということである。
ヒトであれば、Y染色体上にある遺伝子によって性が決まる。
生物によっては、興味深いことに、性が気温によって決まるものもいるようだ。
たとえば、ウミガメは、砂浜に穴を掘って卵を産みつけた後、地表に近い方と遠い方との温度差で雄雌が決まるという。
本書を読んで、性の決定プロセスについて少し踏み込んで知ることで、性スペクトラムという考えへの理解も深まるはずだ。
性差は細胞レベルで存在している
本書の主張は、私たちは常に男性70%とか女性30%とかを行ったり来たりしているということで、決して一つの性に固定されることはないというものだ。
ここで一つ疑問が生じる。
先ほどのように、性の決定プロセスがいかに多様であろうとも、いずれにしろオスメスが決まるということであれば、性がスペクトラム上の様々な位置を行き来するという考えは、一見して矛盾しているようにも思える。
しかし、一度決まった性はその後絶えず揺らいでいるものだ。
揺らぐ要因として、第一に性ホルモンの働きがある。
詳細は本書に譲るが、性ホルモンの量はライフステージの各段階で常に変化していて、性の揺らぎを作っている。
さらに、本書では話を進めて、心臓や脳などの臓器ごとにも性差が存在すると主張する。
わたくしたちの身体の性は細胞に求めることができる。つまり「細胞が性を持っている」という話をしていきます。
一体、細胞が性を持つとはどういうことなのだろうか?
この続きはぜひ本書で確かめていただきたい。
ダイバーシティとは何かを考える
ダイバーシティとは一体なんだろう?
多くの人は、ダイバーシティと言えば、性別や人種、障がいの有無など、目で見える多様性に注目しがちである。
しかし、本書を読んでわかるのは、個人の中でさえ多様性が存在するということだ。
男性らしさや女性らしさというのは、常に変化しているもので、知らず知らずのうちに私たちの価値観や思考に影響を及ぼしている。
時にホルモンバランスが崩れることで、体調を崩したり嫌な思いをすることがあるかも知れないが、性とはそういうものなのだと理解していれば、自分の身体の変化を少しは受け入れ易くなるかもしれない。
ダイバーシティとは、他人を認めること、つまり個人を尊重することである。
ダイバーシティを考える前に、本書を読み、自分の中に存在する多様性を認めるところから始めてみるといいだろう。




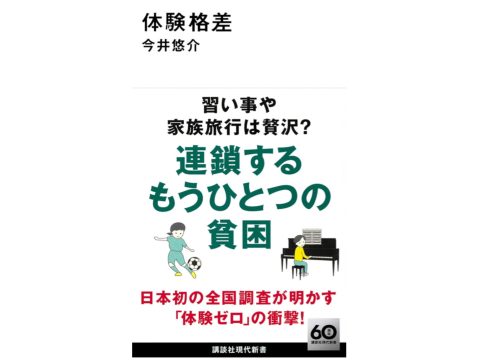
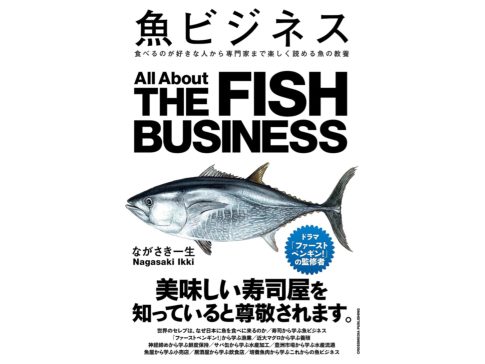
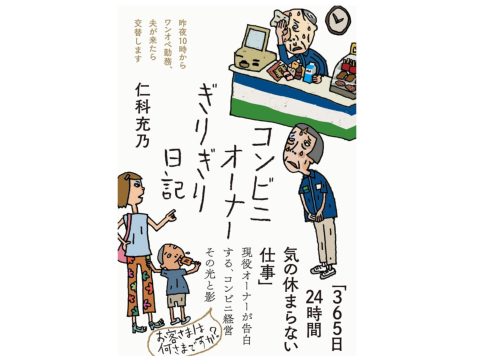
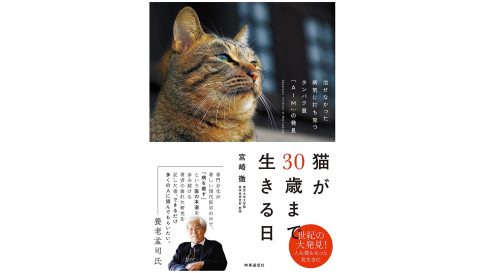


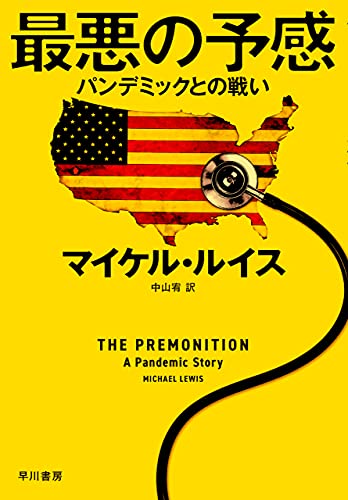
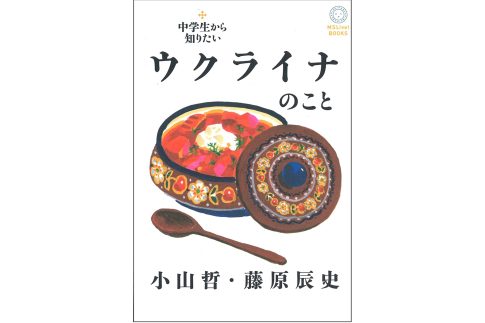




コメントを残す